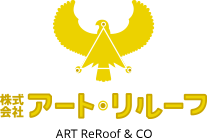なぜ緑色?
関東は桜満開、春本番で外歩きも心地好い季節になりましたね🌸
屋根屋の本能か😅外を歩いていると自然と屋根に目がいきます。
先日名古屋城へ観光に行ったところ、緑色の屋根が目に飛び込んできました。
お城の屋根瓦といえば黒っぽい色を想像していたので、
なぜ緑色なんだろう?と気になり調べるとサビが原因とのこと😮
サビる瓦なので陶器瓦ではなく金属瓦です。
江戸時代になると金属加工の技術が進み、金属瓦が多く使われるようになりました。
銅瓦は高価だった為、一般家庭には普及しませんでしたが城郭などの屋根材には多く使われていたそうです。
その理由は軽さと高い耐火性。
1615年、徳川家康によって建てられたこの名古屋城、天下統一に向けて幕府の体制を確立したいという思いが込められていたので、高価な銅瓦を使うことで権力を誇示する意味も大きかったように感じられます。
さて、なぜ緑色なのか?
銅瓦の表面は経年に連れ雨水によって酸化し、緑色の緑青(ろくしょう)と呼ばれるサビが発生します。
古い10円玉に緑のサビがついているのを見たことがありませんか?あれと同じサビです。
この緑青が銅表面の保護被膜となり、長期間にわたる耐久性を発揮するのです。
サビと聞くと劣化をイメージするのが一般的ですが、このように役に立ってくれるサビもあるのですね✨
春うらら、外出の際に屋根を見上げてみると様々な色や形があり楽しいですよ🏠